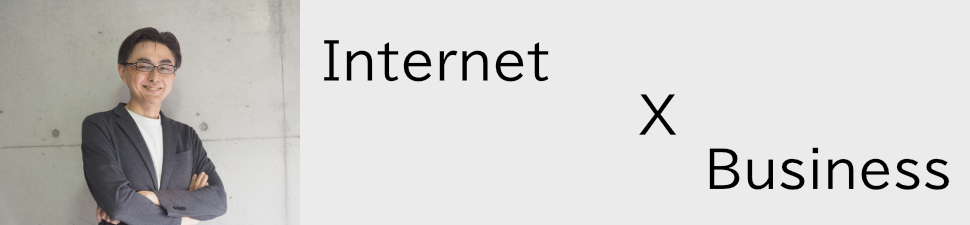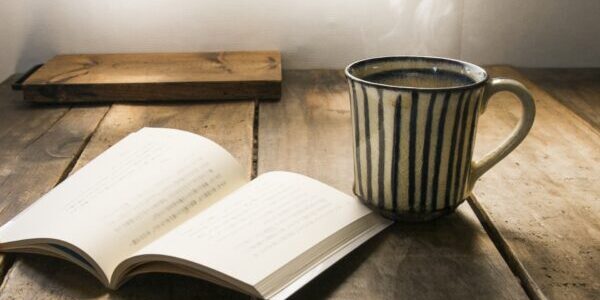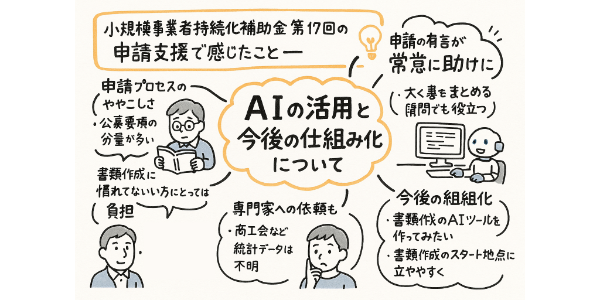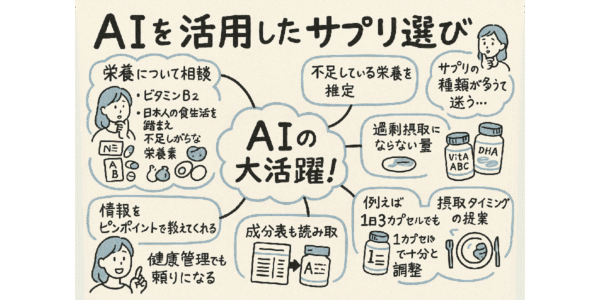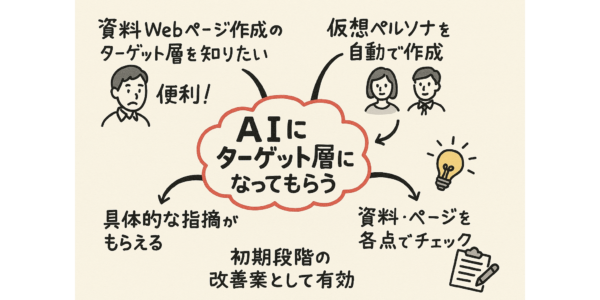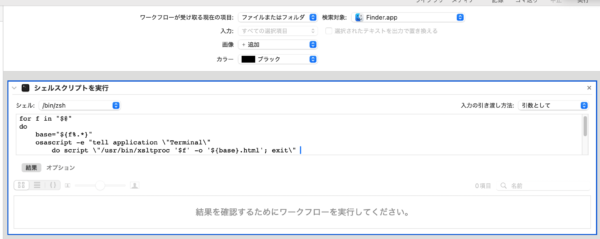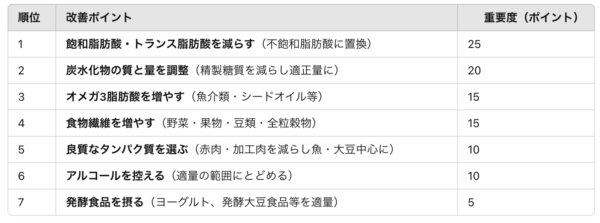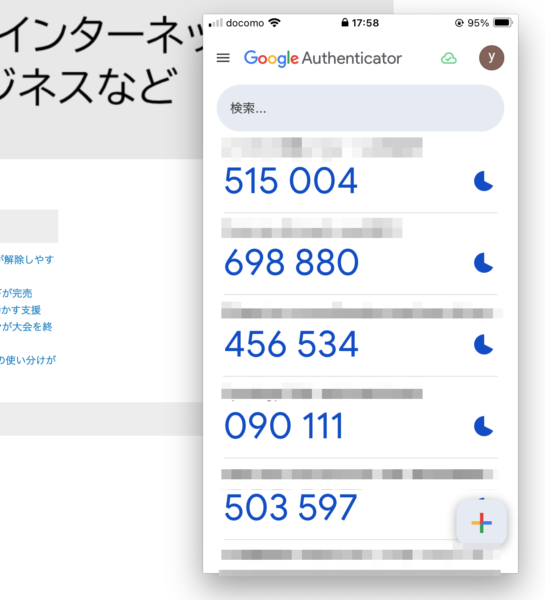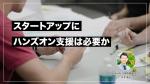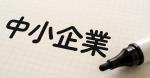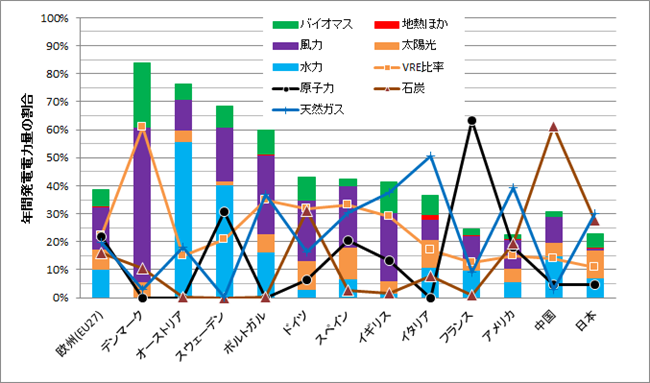何やら重大発表があるとしていたAffinityですが、ほんとに重大発表でした。
今までAdobe製品の代替的な位置づけで、
Affinity Designer が Adobe Illustrator、
Affinity Photo が Adobe Photoshop
Affinity Publisher が Adobe InDesign
に対応するものでした。
Adobe製品はデザイン業界のスタンダードで高機能ではあるんでしょうが、今は高額なサブスクでしか使えずデザイン業務がメインでない場合は使いづらいという状況があります。そんな中、数千円くらいの買い切りで使えるソフトとしてこれらAffinity製品は重宝して使っておりました。
それらが、なんと無料化。しかも3つのソフトが1つになって、ソフトの使い分けを意識することなく1つのソフトで何でもできるようになると。
こういうソフトは「みんなが使っている」状態になると、ハウツーなどの情報がネット上に溢れてきますが無料であれば使う敷居が大幅に低くなるので、そっちのステージに入っていくかもしれませんね。少し前は印刷物などの納品データはAdobe Illustrator形式のみだったりするところも多かったですが、現在は印刷用フォーマットのPDFなんかでも納品できてキレイに印刷できるようになっているので、必ずしもAdobe製品でなければいけないというケースは少なくなってきました。
ずっと愛用してきたソフトなので、その進化版がスタンダードになると色々と便利になって助かります。成果物だけではなく、編集中のファイルも共有して使うということもできるケースが増えますしね。
完全無料にするということで継続性として大丈夫なのかという心配はありますが、無料化を期にみなさん使ってみてはいかがでしょうか。便利ですよ。